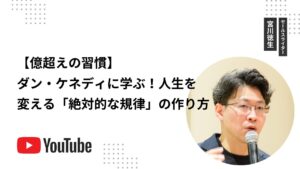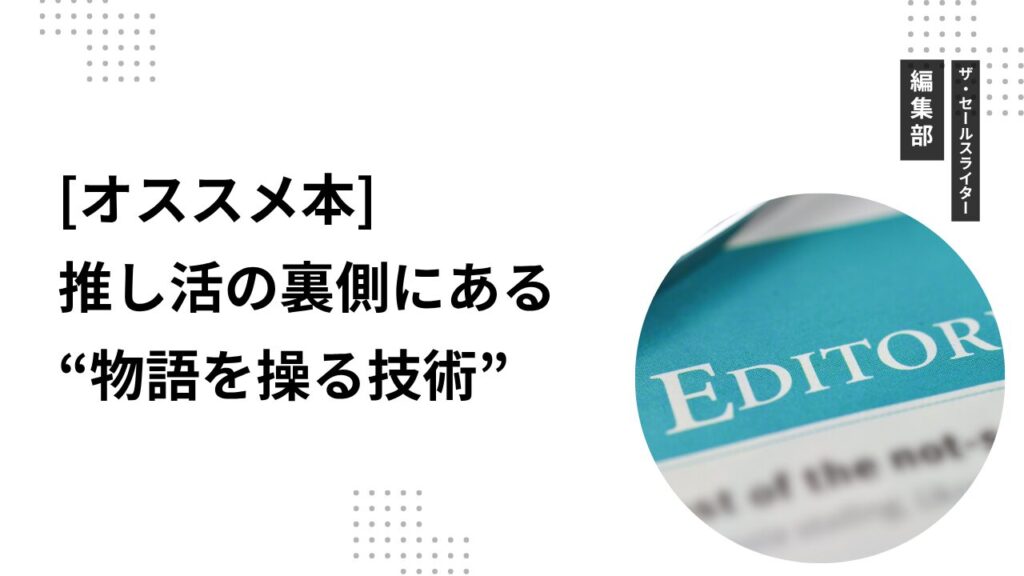
こんにちは。
株式会社バリューイノベーションジャパンのリサーチャーXです。
今回の推し本はコチラです!
■ イン・ザ・メガチャーチ (日本経済新聞出版)
https://amzn.to/491HMIN
普段はビジネス書や実用書をご紹介することが多いのですが、
今回は「小説」です。
といいますのも、書店でこの表紙帯コピーに目を奪われ、
手に取らずにはいられませんでした。
「神のいない国で人を操るには“物語”を使うのが一番いいんですよ」
ライターやコンサルタント、マーケターな方であれば、
きっと普段から物語(ストーリーテリング)を
どう機能させるか?と考えていらっしゃるのではないでしょうか?
そんな中で出会ったこの一文。
見過ごすことはできません!
物語のテーマは、ファンダム経済つまり“推し活”です。
今や大きな経済圏を生み出すほどの影響力を持つ推し活。
マーケティング界隈の住人としては、当然関心のある分野です。
「推し活って、熱量の塊だし、何かヒントになるかも」
そんな軽い気持ちでページを開いたのですが…これは完全に誤算でした。
ストーリーに引き込まれすぎて、読了後、しばらく動けませんでした。
しんどい。とにかく、しんどい。
※小説なのでネタバレは避けますが、少しだけご紹介を。
物語は3つの視点で進んでいきます。
・推し活に「のめり込んでいる」側
・推し活に「のめり込んでいた」側
・推し活を「仕掛ける」側
のめり込む側が推し活に没入することで得られる、羨ましいほどの “光”。
そして、その裏にある真綿で首を絞められるような“影”。
それだけでも胸が苦しくなるのに、仕掛ける側の残酷なまでの冷徹さが、
さらに追い打ちをかけるのです。
たとえば、仕掛ける側がファンへの向き合い方を示すこんな一文。
----------------------------------
これはあなたの物語、なんていう宣伝文句はもう見慣れて久しいですが、あれも受け手の自他境界を曖昧にして、没入と視野狭窄を煽る手法の一つです。
引用「イン・ザ・メガチャーチ」p.185
-----------------------------------
普段、私たちは現場で物語の力を“伝える技術”として使ったりしますよね。
だからこそ、この描写はただのフィクションとは思えませんでした。
技術としての物語を決して無自覚に使ってはいけない。
「仕掛ける側」の責任。
その強さと怖さ。
そんなことを思い知らされます。
そして「のめり込む」側に対しても
テレビやニュースをみていると推し活はキラキラしていて
充実しているように見えます。
実際、私の友人にも、アイドルの推し活で全国を飛び回っている人がいます。
その夢中になっている姿が、本当に羨ましく
「情熱を注げるものがあるって、いいな」と。
ですが、この小説を読んだ今、
その感情が少しだけ違うものに変わりました。
「『羨ましい』だなんて気軽に言っていいことじゃないのかも…」
そんなふうに、胸の奥がズシンと重くなるような読後感がありました。
こちらの本は、
「マーケティングのヒントになりそう」
「ファンダム経済の実態が気になる」
くらいの気持ちで読むと打ちのめされます。
ですが、だからこそ。
“物語”が人に与える影響の強さ。
それを扱う側が持つべき覚悟と視点。
その「向こう側」を知るきっかけとして、これ以上ない一冊です。
読後、言葉がなかなか出てこなくなると思います。
でも、静かに効いてきます。
もし、あなたが
・ストーリーで人を動かす仕事をしている
・「推し活」心理の光と影に関心がある
・熱狂や信仰の構造に興味がある
そんな方なら、きっと大きな気づきがあるはずです!
ですが、“気軽に”はオススメできません。
それでも“深く考えたい”方には、強く強くオススメします。