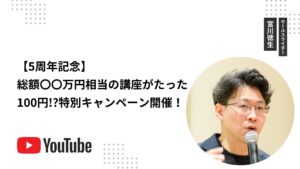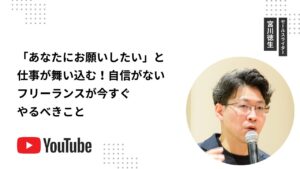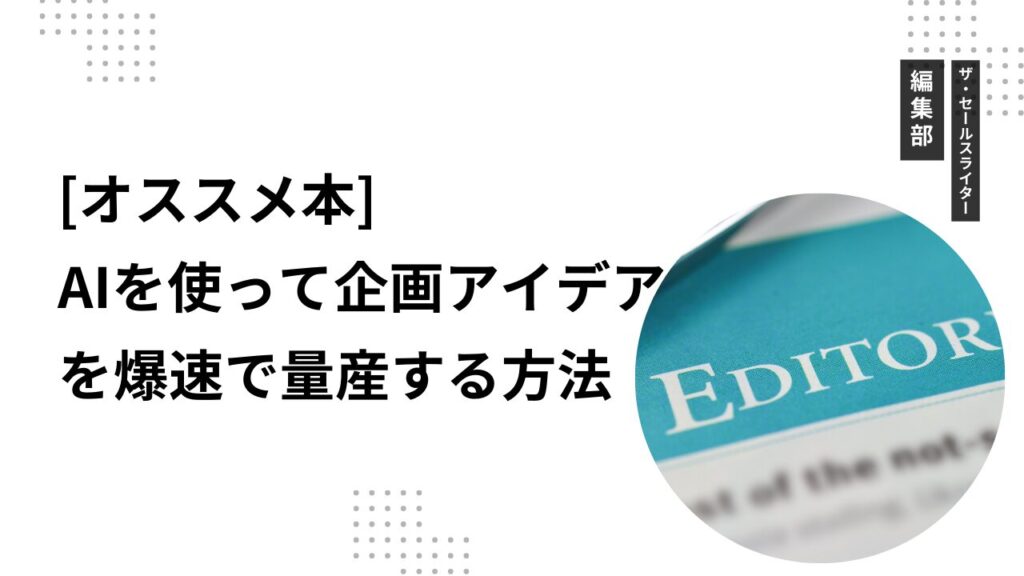
※この記事にはAmazonアフィリエイトリンクが含まれています。
こんにちは。
株式会社バリューイノベーションジャパンのリサーチャーXです。
お盆休みもそろそろ終わりが見えてきましたね。
このお休み期間、どんなふうに過ごされましたか?
私はというと、積読になっていた本をまとめて読み倒す、
そんなインプット重視の時間にしていました。
その中で、特に「これは…!」と思ったのがこちら。
↓
■ AIを使って考えるための全技術
「最高の発想」を一瞬で生み出す56の技法
https://amzn.to/4lmwwJf
こちらの本、特にこんな悩みを抱えている方におすすめです。
・アイデアが出てこない…
・限られた時間で大量のアイデアを出す必要がある
・そもそも「アイデアの出し方」がよくわからない…
.
実際、弊社でもコピーや
アウトプットのレビューをしていると、
「うーん、それ以前に“このアイデアでいいの?”」
という“そもそも論”に立ち返ることがよくあります。
アイデアがズレていたり、弱かったりすると、
どれだけ言い回しや表現を整えても、やっぱりパッとしない。
逆に、アイデアがバシッと決まっていると、
コピーが多少ラフでも「これはいけそう!」
という空気感が出るんですね。
つまり、「コピーが難しい…」と感じるときほど、
実はアイデアそのものが“弱い” 可能性が高い、ということ。
とはいえ、
「じゃあどうやってアイデアを出すの?」
という壁がある。
しかも、この壁、見た目よりだいぶ高い…。
私も昔、思ってました。
「アイデアって、結局“天才のひらめき”じゃないの?」
と。
でも、あるとき耳にした言葉が、その思い込みを変えてくれました。
「アイデアは、既存の要素の新しい組み合わせ」
たぶん、あなたも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
これを聞いた瞬間、
「あ、なるほど。“無から生み出す”んじゃなくて、あるものを組み合わせるのか!」
と、ちょっとだけ気がラクになったんです。
でも、すぐに次の疑問が襲ってきます。
「その“あるもの”って、どう集めるの?」
「“新しく組み合わせる”って、どうやるの?」
わかるけど、わからない。
やれそうで、やれない。
アイデアって、そういう存在だったりしますよね。
そんな中で出会ったのが、この本です。
本書では、アイデア発想のプロセスを
「連想 → 想像 → 創造」という流れで解説してくれています。
-------------------
最初に「連想」によって物事や概念が結びつき、広がりを持ちます。次に「想像」では、連想で得たことをヒントにして自由に発想が拡がります。そして最後の「創造」で、これまでに想像したヒントがアイデアとして具体化していきます。
――引用『AIを使って考えるための全技術』p.38
-------------------
これこそまさに、
「既存の要素を新しく組み合わせる」ための“実践ルート”でした。
そして、この流れをAIが手伝ってくれるというのが、
本書が示してくれた道です。
本書には、連想を広げ、思考を深め、形にしていくための
具体的な技法が56個、これでもかというほど紹介されています。
「ただのプロンプト集かな?」
と思われるかもしれませんが、違います!
もちろん、コピペで使える
プロンプトも収録されています。
でも、その裏にある思考の構造や意図の設計が、
ていねいに言語化されている。
・なぜこのプロンプトなのか?
・どんな経緯でこの形に至ったのか?
・AIの出力からどう選び、どう活かすのか?
すべて、著者の方の思考回路とともに語られているんです。
そして、そのプロンプトは特典としてダウンロード可能。
チートシートまで付いていて、実用面でもすぐに使える設計です。
本のページ数は驚異の682ページ。
でも読みやすく、サクサク進みます。
タイトルにある
「AIを使って考えるための全技術」の「考える」。
この「考える」とはどういうことなのか、
そして、どうAIと共に実行するか。
その“思考の筋トレ”が詰まった一冊です。
・プロンプトのコピペから卒業したい方
・AIを使って“本物の思考スキル”を鍛えたい方
・自信を持って「これだ!」と言える
アイデアを出せるようになりたい方
そんな方に、心からオススメします。
そして、最後にひとつ。
この本を読んで感じたのは、
「AIと一緒に考える」というのは、
単に効率化の話ではない、ということです。
いいアイデアが浮かばないときって、
「自分の引き出しの少なさ」や
「思考の浅さ」に直面して、
なんだかちょっと落ち込んだりしますよね。
でも、そこにAIという相棒がいてくれると、
角度を変えて問い返してくれたり、
想像していなかった切り口を投げてきたりする。
するとその結果、
「あれ!?今までとは違う視点で考えられてる!」
と実感できる瞬間がくるんです。
そしてそれが、
ビジネスの場面で提案の切れ味、
思いつくスピードや幅として
確かな武器になっていく。
だからこそ、ただ便利に使うだけじゃなく、
“AIを使って自分の思考を鍛える”
という視点を持つことが、
これから本当に重要になってくると感じました。
思考停止にならずに前に進みたい。
自分の仕事にもっと説得力を持たせたい。
そんなときに、この本は確実に力になってくれます。
ビジネスの現場で、アイデアと精度が両方求められる人にこそ、
手元に置いておいていただきたい1冊です。
考える力を、ちゃんと成果につなげたい人に。
自信を持ってオススメします!