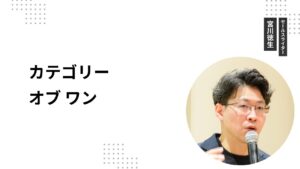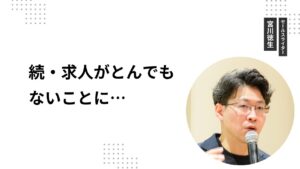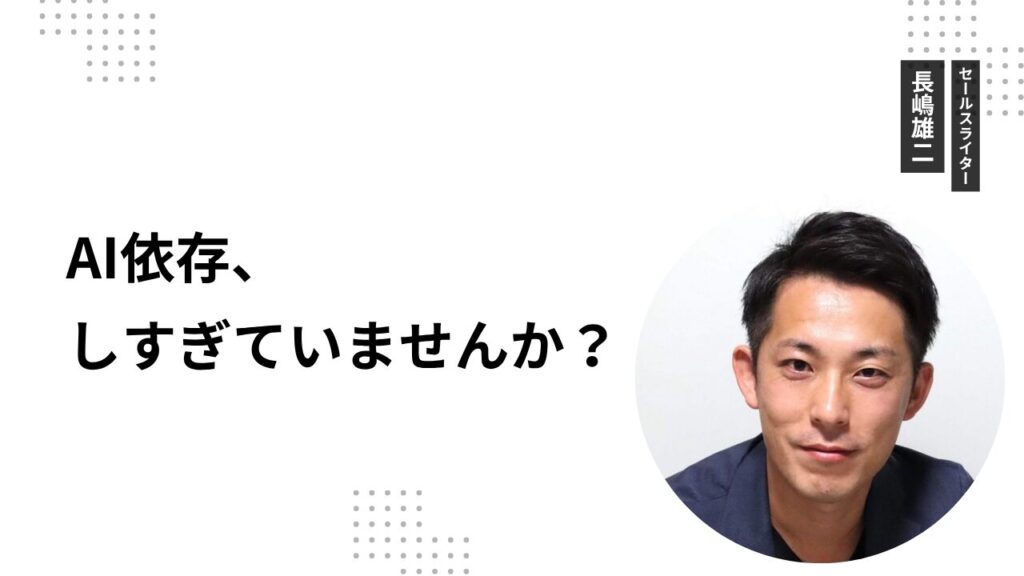
From:長嶋雄二
先日、
訳あって
両親の田舎に帰省していました。
静岡の伊豆地方なので
超がつくほどの田舎なのですが、、、
久しぶりに、懐かしい海の匂いや
田舎特有の香りや雰囲気には
どこか落ち着く感覚がありました。
何よりも胸に残ったのは、
昔からお世話になっていた親戚のおばちゃんが
「まぁまぁ、よく来たねえ〜」と
手を握ってくれたときの温もり…
なんか、こういうのって言葉ではないですよね。
「人の温度」みたいなものに、
ついつい忘れかけていたものを
思い出させてもらえたような気がしました。
それは、効率でも合理性でもない。
そこにちゃんと「気持ち」がある、、、という感覚。
この『温度感』みたいなものを、
僕たちは、マーケティングの現場で見失っていないか・・・?
そんなことを考えていたのですが、
ちょうど、その日の夜に、、、
ある“違和感”を感じることがありました。
それは、知人のコンサルから、
「このメルマガをレビューしてほしい」
と依頼が来たのですが、、、
一見すると、コピーは整っている。
文法も正しい。
言葉も丁寧で、それっぽく良い感じ。
でも、なんだか引っかかるんです。
「これ、絶対AIが書いたな…」って。
その違和感、具体的に言うと
・AIに書かせると生まれがちな、無意味なスペースが多すぎる
・その人“らしさ”が消えて、誰が書いたか分からない文章
・だからこそ、感情が動かない
みたいな状態。
実際、ChatGPTやGeminiなどを使って、
コラムやサービス紹介文を作っている方も多いと思います。
たしかに、便利です。時短にもなりますし、
「まず1本書いてみる」にはピッタリのツール。
でも!・・・
そのまま出していませんか?
そのままWebにアップしたり、SNSにコピペしていませんか?
今、改めて強く伝えたいのは、
AIは、あくまで“たたき台”であるべきだということ。
なぜなら、読むのは人間だからです。
僕たちはマーケティングの世界でよく言います。
「感情を動かすことが、行動につながる」と。
でも、AIがつくった文章って、
どこかで“体温”が感じられないものが多い。
特に書き手のことを知っていればいるほど
その違和感は大きく伝わります。
「きれいにまとまっているけど、
読み終わったあとに何も残らない」
これが最大のリスクなんです。
だからこそ必要なのは
「この人の言葉だ」と感じさせる工夫です。
たとえば、、、
・自分が話した音声をAIに要約させてベースにする
・過去に書いたブログを学習させて、そのトーンを再現する
・AIに「私らしく書いて」と頼むのではなく、最後に必ず自分で仕上げる
こうするだけでも、
「らしさ」や「熱量」が格段に変わります。
たとえば、整体院やエステサロンで
「AIに接客も全部任せてます」
と言われたら、どう思いますか?
「それ、大丈夫…?」って思いますよね。
患者さんの表情を見ながら、
ちょっとした言葉で安心させたり、
現場で起きた小さな異変にすぐ気づいたり…
そういう“空気を読む力”って、
人間だからこそできるものです。
AIは便利。
でも、、、
便利さの先にある
『その人らしさ』を手放したとき、信頼が離れていくと思っています。
これは、メルマガでも、LPなどのコピーでも
まったく同じことが起きている
ってことなんです。
もちろん、僕もAIはガンガン使っています。
でも、そこで重要なのは
「削ぎ落とされたリアル」を残すこと。
過去の体験や、クライアントとの会話、
現場で得た気づきこそが、読み手の心を打つからです。
AIに依存しすぎる先にあるのは
『無個性』という危険性だと思っています。
読み手に響く文章とは、
完璧さよりも、『あなたらしさ』がにじむかどうか。
便利な道具であっても、
魂を込めるのは、やっぱりあなた自身なんです。
『信頼をつくるのは、あなたの“にじみ出るリアル”』
ここを忘れないでくださいね。