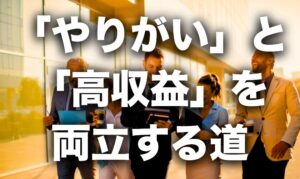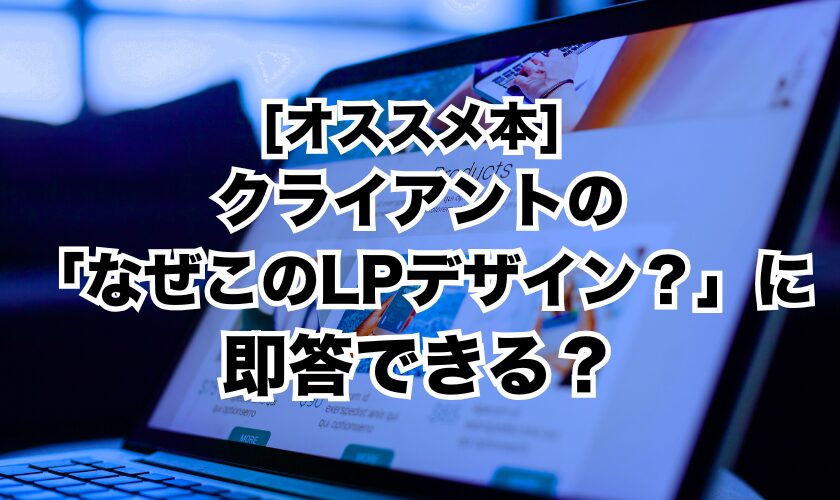
こんにちは。
リサーチャーXです。
今日の推し本はこちらです!
↓
■ デザイナーは何を考え、どう作っていくのか? WebデザインプロセスBook
現場でクライアントさんのサポートをしていると
LP作成やWebサイト構築に携わる機会が
あるかと思います。
そんなとき。
自信を持って制作できてますか?
クライアントさんから質問を受けた際に
「なぜ、そう作ったのか?」
の意図を明確に説明できてますか?
はたまた、ライター・コンサルとして
外部パートナーのデザイナさんに
制作を依頼したとき。
意図していたものと
違うデザイン案があがってきたり、
改善してほしいのだけれど
うまく言語化ができなかったり、
感覚的な伝え方になってしまう…。
もし、そんなお悩みをお持ちでしたら、
悪いことは言いません。
/
今すぐ、こちらの本を手に取ってください。
\
こちらの本、私は読み終えるのに
2時間30分ほどかかったのですが、
確実に “2時間30分前の自分” から
レベルアップしました。
もちろん、制作実装の部分においては
実際に手を動かす必要はありますが、
(そのために購入者特典として
サンプルやテンプレがダウンロードできる)
わずが2時間30分で
LPやサイトを違った視点から見る「目」を
手に入れることができたのは間違いありません。
そんな「目」。
言い換えますと
考え方や思考のしかたです。
こちら、本書のタイトルそのものズバリで、
「デザイナーは何を考え、どう作っていくのか?」
「Webデザインプロセス」
と Before After を通じてデザイナさんの
“思考回路” “プロセス” を覗ける内容になっています。
「ここをこんなふうに変わりました」といった
ただの Before After ではありません。
BeforeとAfterの “間”。
このプロセスを見ることができちゃうのです。
実際に Before が After になるまでに
何回も調整が入ります。
それが、
どういう意図で、どう変わっていったのか?
この「思考」と「試行」こそが、
本書から学び取るべきポイントです。
もし、単なるBefore と After だけを見せられたら
「ああ、すごく良くなったね」
で終わってしまう。
ところがどっこい、
BeforeとAfterの “間” の「思考」と「試行」に触れ、
過程を追うことで自分の中に再現性を
持つことができるようになるわけです。
この再現性。
ライター・コンサルのあなたなら
どの案件でも再現性を持って
取り組むことのできる重要性は、
きっとご理解いただけるのではないでしょうか?
さらに「思考」についても
難しい文章でズラズラと書かれているのではなく、
画像を使い、シンプルかつやさしい言葉で
解説してくれていますのでとてもわかりやすい。
また、制作事例として以下のように
実際の案件でありそうな内容で
解説されていますので、自分ごとにもしやすいです。
---------------------
《コーポレートサイト》
・国際特許事務所
・介護施設
・製造業
《ECサイト》
・インテリアショップ
・ペットウェア
・登山用品
《シングルページ》←LP
・学習塾
・観光ホテル
・イタリアンレストラン
《採用サイト》
・総合病院
・野菜農園
---------------------
これら一つ一つの事例に
ヒアリングシート
↓
ワイヤーフレーム(サイトの骨格)
↓
デザイン制作
の流れを見ることができます。
本命の「デザイン制作」の行程では
「思考」と「試行」が繰り広げられます。
さらに、
画像写真の使い方やパーツの置き方などを
脳科学や心理学的な観点から
言語化してくれていますので、
なんとなくで感覚的にやっていたことを
説得力を持って相手に説明できる
チカラも与えてくれます。
「どこをどうやって調整していけばいいのか?」
「なぜそこを調整するのか?」
をフワフワとなんとな〜く、ではなく、
明確な意図と言葉を持って進めていける。
これ、めちゃくちゃ強いですよね。
実際、ライター・コンサルとして
制作代行業務で実装の部分も請け負った場合、
クライアントさんに対して
「なぜそうしたのか」
「なぜそうなっているのか」
を言葉で説明することを
求められる場面も少なくないと思います。
そんなとき、
「なんとなくそうしました」ではなく
マーケティングの視点や
セールスファネル全体の流れから
「このLPはこういう役割ですから、
デザインではこういう意図で配置しています」
「ユーザー導線として
こういう落とし込みが必要なので、
ここの部分のイメージは
こうデザインしています」
というように
狙った施策や打ち手とからめて
説得力を持った言葉で言い切れる。
このスキルほしくないですか?
また、
作成したLPやWebサイトを
クライアントさんに見せたとき
「ウチの業界ではこういうのはちょっと…」
「もっとかっこよくして」
というように
クライアントさんのひとことで
骨抜きにされてしまうような状況。
それに対して、
相手をねじ伏せるためではなく、
お互いに納得感を持って進めていける。
マーケティングの視点から
自信を持ってデザインを合わせた
プロとしての提案ができる。
そんなスキルがほしい。
もし、そんなふうに思っているなら
ぜひお手にとってみてください!
・・・
こちらの本は、
そんな、現場で使える具体的ノウハウとして、
オススメなのはもちろんなのですが、
ワタクシ的に一番の “推しポイント” は
最終ページにありました。
----------------------
私はふだんからデザインのチェックバックに限らず、「修正」という言葉を使いません。変更や直しの依頼などはすべて「調整」で統一しています。「修正」は、よくない点を改めるという言葉です。発注側の不備や意向にも関わらず「修正してください」と言われると相手は違和感を覚えます。
引用「デザイナーは何を考え、どう作っていくのか? WebデザインプロセスBook」p.253 より
----------------------
※ チェックバック = 修正指示
ライター・コンサルの場合は、
このチェックバックを
・クライアントさんから受ける側
・デザインさんに出す側
の両方になりうる立場かと思います。
その立場で使うこの「修正」という言葉。
その言葉を受け取ったときの相手の感情。
私はこれまでここを意識せず、
「修正」という言葉を何気なく
使ってしまっていたと反省しました。
それに対して「調整」って言葉、いいですね。
どことなく
ゴールに向かって前向きに
積み上がっていく響きがあります。
「修正」だと一方的な感じがしますが、
「調整」は一緒に作り上げていく感じ。
…と、
ここまでこのメールを書いてきて
今、気がつきました。
この本は、
LPやWebサイト制作のノウハウに見えて
実は、
相手(クライアントさん、デザイナさん)との
関わり方の本ですね。
同じゴールを目指す同志として、
お互いの意図やねらいを深く理解して
受けとめ、伝える。
そのための本なのかもしれません。
そんな大切な気づきも与えてくれるこちらの本。
ライター・コンサルの方にこそ
読んでいただきたい内容です。
ぜひお手にとってみてください!
P.S.
ちなみにこちらの本、
LPやWebサイトだけでなく、
なんとバナーの調整プロセスまでもが
Chapter 5で説明されています。
この部分だけでも
かなりのスキルアップが
望めてしまうこと受け合いです。