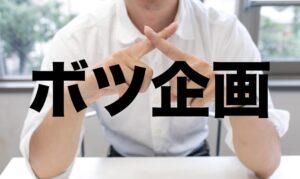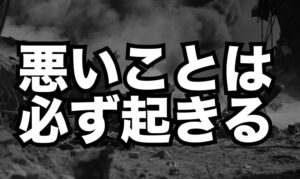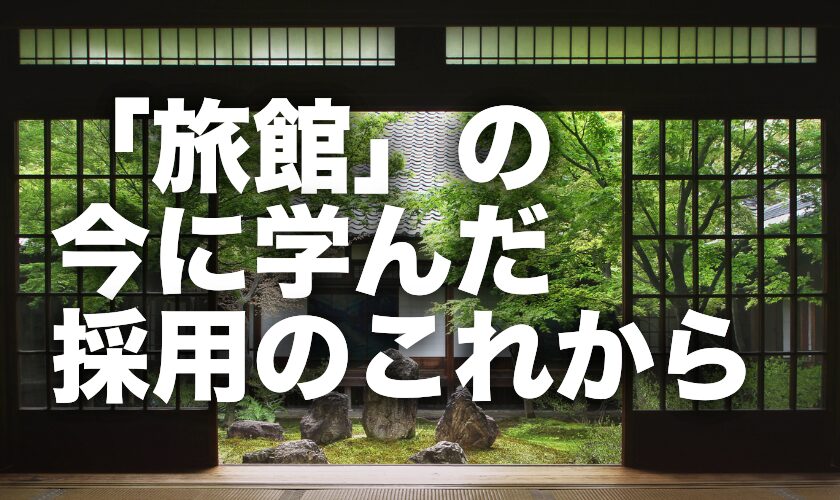
From:長嶋雄二
先日、鬼怒川で
ある旅館の社長さんと
お話していたとき、
ふとした話の流れで
こんなことをおっしゃっていました。
「昔は、若い子が“働かせてください”
って玄関先に来てくれたものなのよ。
でも今は、“旅館が好きです”って
来てくれる子すら、めっきり減っちゃったの。」
この言葉を聞いて
ちょっと胸が詰まりました。
旅館はただの“宿”ではなく、
その土地の文化や
人の温度がにじみ出る場所。
そんなふうに僕は感じているからです。
というもの、
僕は父親の出身が伊豆なので
ほんの少しですが「旅館文化」にふれて
育ってきた背景があり
旅館が彩ってくれる
町の雰囲気って、なんか好きだったんです。
幼いながらに。
でも今、「人」がいないことで、
その灯が消えかけている...
なんかすごく、寂しいですよね。
そして、その影響もあってか、最近では、
外国人の方の力を借りる旅館も増えています。
ただし
「日本語マニュアルがない」
「教える人がいない」
「文化の違いで続かない」
そんな現場の声は
やっぱりたくさんあるようで…
教える仕組み、育てる仕組みが整っていないと、
せっかく来てくれた人も定着しません。
さらに話が進んでいくと、、、
・求人広告を出しても反応がない
・ようやく来た子も数ヶ月で辞めてしまう
そんな声は、やっぱり
どの旅館からも聞こえています。
でも、なぜ?
なんで『求人広告を出しても反応がない』のか?
もう旅館がダメ?
古い伝統だから?
時代じゃない?
・・・僕はそうは思いません。
一番の問題は、
・この旅館で働くと、こんな未来があるんだ!
・自分が関われる、ここだけの物語があるんだ!
というビジョンやストーリーが、
旅館側から、発信されていないこと。
言い方を変えれば、
『働きたくなる理由』が、ないんです。
たとえば今回、
お話した社長さんの旅館では
もうすぐ創業60周年を迎えるそうです。
この60周年のイベントに向けて
「旅館をリブランディングするプロジェクト」
が進んでいるそうなんですが…
例えばここで、、、
若手スタッフが中心となり、
館内のリニューアル案を出し、
地域との連携イベントを企画し、
SNSで発信まで担当していく・・・
そうした活動や背景を
若手スタッフ自らが発信していくことが増えていけば
同じ世代にもその情報は伝わるし、
そこに共鳴する人がでてきますよね。
・いいなぁ
・私もそんなことしてみたい!
・なんか楽しそうだな!
興味をもってくれるきっかけなんて
そんな些細なことからでいいんです。
そして、そうした活動を通じて
若手スタッフも「自分がつくる旅館」という誇りが生まれ、
やりがいが育つと思うんですよね。
なので、
これからの採用に必要なのは、
「人が来るのを待つ姿勢」ではなく、
“この土地、この場所、この仲間とつくる未来”
に人を巻き込む仕掛けなんだと思います。
とはいえ、、、
これは一つの旅館だけでは難しいことも
わかっています。
地域全体で、
『人を育てるための仕組み』が
本当は理想できなんですよね。
・外国人スタッフの育成研修
・若手を支援するワークショップ
・地元とつながるプロジェクト設計
・新人研修を共有できる地域カリキュラム
こんな取り組みが、
これからの旅館を変えるカギになるよね…
そんなことを
先日も少しお話しさせて頂きました。
旅館は、地域の「顔」です。
そしてその顔をつくるのは、やっぱり「人」。
求人広告を打つ前に。
研修マニュアルを整える前に。
まずは「どんな人と、どんな未来を描きたいか」・・・?
そこを一緒に見つめ直すことが
大切なんだな、、、と改めて感じました。
そしてこれは、
旅館に限ったことではないですよね。
・医療業界
・介護業界
・製造業界
・建築業界
・IT業界
どんな業界の採用であっても
その事業における「人」と「未来」を
どう見せていくのか?伝えていくのか?
そんな視点で、もう一度
採用を見直してみたら、
きっと、まったく違う結果が見えてくるはずです。
「人を探す」のではなく、
「未来を語る」
これ、あなたも試してみてくださいね。